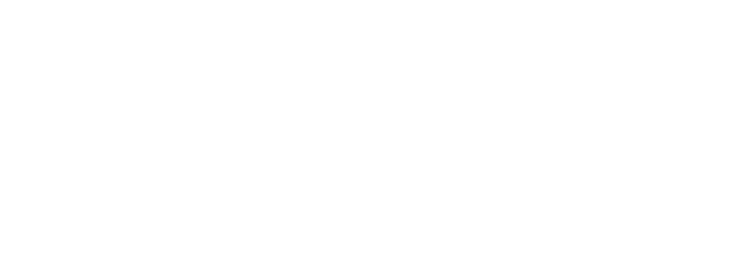なぜ日本のライブコマースは「安売り」から「ストーリー重視」へシフトしたのか?〜中国市場から予測する次の波
2025.09.08
1. 「ライブコマース=セール」のイメージは、もう古い!
数年前、日本にライブコマースという言葉が上陸したとき、多くの人が抱いたイメージは「時間限定の激安セール」や「テレビショッピングのデジタル版」だったかもしれません。確かに、初期のライブ配信は、在庫処分やタイムセール的な使い方をされることが主流でした。
しかし、私たちSホールディングスが現場で体現しているのは、このイメージとは全く違う、新しい波です。
現在のライブコマースの主戦場は、「安さ」ではなく「共感」へ、そして単なる「販促」から「コンテンツ」へと、劇的にシフトしています。この変化の背景には、世界最大のライブコマース市場である中国のトレンドと、日本の消費者が求める「本物」の価値があります。
2. 中国市場にある「熱狂」と「エンタメ化」の凄まじさ
ライブコマースで桁違いの成功を収めている中国市場は、日本の未来を占う上で大きなヒントになります。
中国のトップ配信者(KOL)が生み出す売上は、日本の多くの百貨店の年間売上を軽く超えます。彼らがなぜ、これほどの熱狂を生み出せるのか? その理由は、ライブコマースを「エンタメ」として徹底的に磨き上げているからです。
- 単なる店員ではない: 配信者は、時にコメディアン、時にファッションリーダー、時に知識豊富な専門家となり、視聴者を魅了する「パフォーマー」として機能します。
- 「信頼」の積み重ね: 視聴者は、配信者が紹介する商品の背景や、配信者自身のライフスタイルに共感し、「この人が良いと言うなら間違いない」という絶対的な信頼に基づいて購入します。
中国では、誰もが知る有名人が地方の特産品を紹介し、わずか数分で数億円を売り上げる例も少なくありません。ここで売れているのは、商品の機能ではなく、配信者の魅力と、商品にまつわるストーリーなのです。
3. なぜ日本の消費者は「ストーリー性」を選んだのか?
この「エンタメ化」と「信頼」の波は、確実に日本にも押し寄せています。
日本の消費者は、もはや「価格が安い」という理由だけでモノを買いません。特に、SDGsやサステナビリティへの意識が高まる現代において、消費者が求めるのは「価値」です。
- 「誰が」作ったか?: 生産者の顔、製造地の環境、商品にかける情熱など、商品の裏側にある物語。
- 「なぜ」作るのか?: 地域の伝統を守りたい、震災後の復興を目指したい、といった社会的な意義や想い。
ライブコマースは、こうした「物語」を、最も人間味あふれる形で消費者に伝える唯一のツールです。
「この魚を育てた漁師さんの笑顔が見たい」「この地方を応援したい」——。
日本の消費者は、ただの安売りではなく、自分の消費行動が誰かの笑顔につながるという「背後にあるストーリー」へと、明確にシフトしているのです。
4. Sホールディングスが仕掛ける「ストーリー主役」の次世代ライブコマース
私たちSホールディングスが、地方再生をテーマに活動しているのは、まさにこの「ストーリー性」の可能性を最大化するためです。
宮城や福岡・山口といった各地で展開する「地方再生プロジェクト」は、単に特産品を売る場ではありません。それは、地方の「情熱とドラマ」を全国に配信する、究極のコンテンツプラットフォームです。
私たちが目指すライブコマースは、単発的な安売りではなく、生産者の想いと消費者の共感をしっかりと結びつけ、持続可能な地域経済を築くための新しいコミュニケーションの形です。
ライブコマースの次の波は、もう始まっています。それは、「安売り」を卒業し、「感動的なストーリー」を主役にする配信こそが、市場を制する、そういう時代なのです。